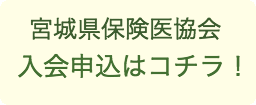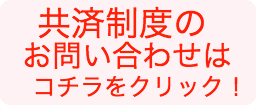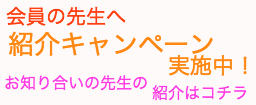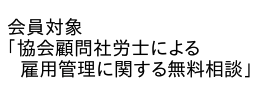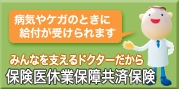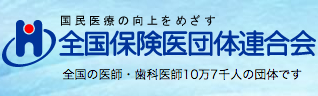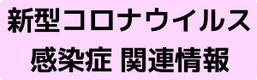シリーズ「女川原発廃炉への道」
福島の被災者の今から 宮城の未来を考えよう
理事 矢崎 とも子
「同情が欲しいのか」「歩く風評被害」など、心無い言葉を投げつけられても「同情、結構。いいのです。明日はあなたがそうなるのです」。いわき市からの自主避難先で起こした原発事故被災者群馬訴訟が結審したのは6月17日。最高裁不当判決で「こんな日本に住むのはもう嫌だ」と思ったが「悔しいから頑張る。この悔しさを、原発をなくす力にしたい」と声を上げ続ける丹治杉江さん。裁判が終わっても「終わりではなく始まり」と、県内のつながりを再度強めるため、今年3月11日に「原発をなくす群馬の会」を結成。「避難者には十分な補償をした」という国と東京電力。彼女が受け取ったのは25万円1回のみという。「住宅問題、いじめ、健康問題、経済的貧困。福島の避難者を取り囲む課題は、何一つ解決していないのに、誰も責任をとっていない」「お詫びはするが謝罪はしない。そんな日本はおかしい」。彼女の訴えは至極当然だ。「風化させようとする力にめげずに頑張るためには、考えることをやめないこと、そして声を上げ続けること」という。
被災者一人一人にそれぞれの人生があり、それぞれに震災体験がある。家族同然の動物も、思い出の詰まったアルバムやひな人形も、持ち出すことすら出来ず。家も故郷も仕事もコミュニティも日常も、すべてを奪ったのは地震や津波ではなく、東京電力福島第一原発事故という人災だ。全国各地で多くの避難者や原告が亡くなっている。「もしも原発事故がなかったら普通に高校に行って、普通に大学に行けたのではないか」「両親は離婚せず、お父さんと遊びに行ったり、反抗したりできたのだろうな」「あの暮らしを返せとどんなに望んでも取り返せない」と声を震わせて被害を訴えながら、「国の責任を認めた判決を得て、原発事故を起こした社会の誤りを正さないといけない」と頑張る人たち。住民の声に耳を傾け、その奪われた人生に思いをはせて考える、そんな普通の裁判官がどれだけいるのだろうか。「避難者の声は裁判の証拠にならないから不要」と耳を傾けることすらしない裁判官に、人としての心はあるのだろうか。12年を経た今もなお自宅に帰れない人たちがいる現実を、ALPS処理水の海洋放出で再び生業を奪うことになる事実に目を向けられる政治家はいるのか。
女川原発の再稼働を控える宮城の住民は、原発は安全ではなく、避難計画も不十分なままなのに40年どころか60年も稼働させ続けようとしている現実を、今再び認識し、明日は我が身と心して、声を上げ続ける必要がある。規制するはずの委員会が規制されるはずの総務省の天下り先という摩訶不思議な事実。戦争による物価高や燃料不足に惑わされていては、子どもたちの未来は守れない。
本稿は宮城保険医新聞2023年3月25日(1809)号に掲載しました。