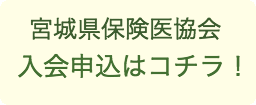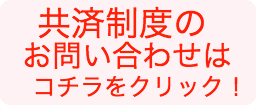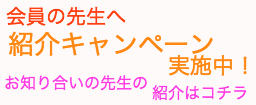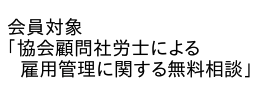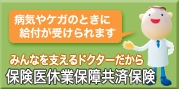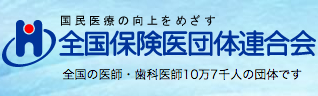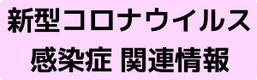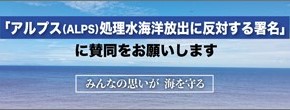シリーズ「女川原発廃炉への道」
安全安心な世界を残すための選択を
理事 矢崎 とも子
東京電力福島原子力発電所と同じ沸騰水型原発である女川原発2号機の再稼働が10月29日と発表された。これまで何度も延期された再稼働だが、今回は本物のようだ。基準値振動を上回る地震に幾度も見舞われ重大な損傷を受けた原発であり、東日本大震災での大事故をすんでのところで免れた被災原発である。微細な亀裂やゆがみは無数にあると言われる。さらに避難計画は絵に描いた餅であり、住民たちの不安はぬぐえない。13年経っても変わらない福島の現状や能登の惨状を、そして人々の心を無視し続けなければできない再稼働だ。
一方シンクタンク「自然エネルギー財団」は、原発や石炭火力発電を全廃しても、製造業の生産規模の維持やデータセンターなどの産業誘致に必要な電力は賄えると分析した。蓄電池の大量導入や送電網の整備によるものであり、求められるのは政府が再生エネルギー拡大を明確に打ち出すことという。
さて2023年8月24日住民との約束を反故にしたまま始まったALPS処理水の海洋放出から1年がすぎた。東電の報告によれば2023年度にトリチウム以外で最も多く放出されたのは半減期5730年の炭素14。その量はなんと4億3千万㏃。半減期21万1千百年のテクネシウム99は3200万㏃。これら2核種はALPSで処理できない。ALPSで処理できるコバルト60、セシウム134/137、ストロンチウム90、ヨウ素129、アンチモン125などですら、数百から数千万㏃放出されている。いくら薄めても総量は変わらないのは当然の事実である。放出してしまえば管理する事は決してできない。人類の歴史をはるかに超えて影響を及ぼし続ける危険な核種は、海を、土を、生き物を汚し蓄積していく。
今我々には、未来の子どもたちに安全で安心して暮らせる世界を残すための選択が求められている。自分に利益をもたらすものだけしか見えない政治家との決別、そして、全ての原発の廃炉を、生きている限り全力で。
本稿は宮城保険医新聞2024年10月25日(1852)号に掲載しました。