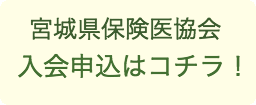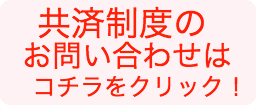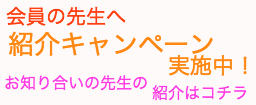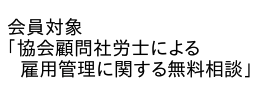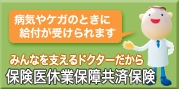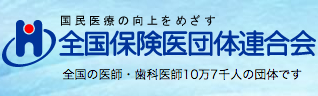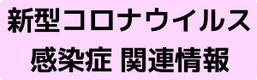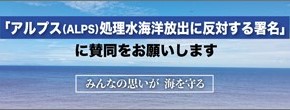シリーズ「女川原発廃炉への道」
再稼働に抗議して(原発模擬実験)
公害環境対策部員 水戸部 秀利
2024年10月29日、多くの県民の不安をよそに女川原発2号機を再稼働した。メルトダウンした福島第一原発と同式のBWR、無数の傷を負った被災原発、13年のブランク、地震津波多発地帯、避難実質不可、東北の電気は足りている、使用済み燃料の処理未定…事故ったら誰も責任を取らないし取れない。案の定、5日後にナットの緩みで停止。しかし11月15日には再々稼働。樋口社長いわく「安全対策に終わりはない」と。住民からすれば、「事故に終わりはない」であり不安は続くことになる。
偶然にも再々稼働の11月15日に、エル・パーク仙台で新婦人宮城県本部主催の「原発から再生可能エネルギーへの転換へ・実践と未来」と題して講演会があり、演者を担当した。
もちろん主催者も参加者も「脱原発」「脱炭素」の基本的な方向を共有しているので、話題の中心を、政府が「石炭火力延命策」にこだわり、「原発回帰・推進」に転換した背景とその理由として持ち出した「温暖化対策」「AIなど電力需要増大」について、為にする世論誘導であることを説明した。政府の言う「資源の少ない日本」も国内の再エネ利用の視点からは全く当てはまらないこともデータをもとに解説した。また、よく言われる再エネのコスト高、不安定、不足論も技術的・実践的に解決されつつあることを説明した。
 理屈っぽい講演の後に、レクリエーションとして写真のような手づくりの「模擬原発」を持ち込んで発電実験のデモを行った。以下解説。
理屈っぽい講演の後に、レクリエーションとして写真のような手づくりの「模擬原発」を持ち込んで発電実験のデモを行った。以下解説。
「原子力発電は、ウランの核分裂反応の熱でお湯を沸かし、高温高圧の蒸気でタービンを回して、その力を発電機で電気に変えています。熱の作り方は違いますが、通常の火力発電と原理は同じです。模擬実験では、安全上ウランや高温高圧の蒸気は使えないので、市販の噴霧器を利用し、原子力の代わりに人力で空気圧を発生させ、その力で圧力タービンを動かし、それを発電機に伝えて発電します。発電した電気で、灯りがつけば『成功』で、めでたく? “原子の火”が灯ったことになります」。
会場からは“原子の火”が灯り、拍手があがった。もちろん「皮肉」の拍手である。
噴霧器の壁には、修理のツギハギの絵も書いている。圧力ベントも付いている。
ちなみに、電球は10ワットのLED球で、携帯用の10ワットの太陽光パネルと充電器で簡単に点灯できる。大掛かりで複雑な原発ではなく、再エネが代行できることも示した。
本稿は宮城保険医新聞2025年2月25日(1858)号に掲載しました。