平成28年 11月24日
宮城県保険医協会
理事長 井上 博之
公害環境対策部長 島 和雄
女川原子力発電所過酷事故時における
原発から30km圏にある医療・介護福祉施設等の避難計画に関する調査(二次)報告②
【調査期間】2016年7月22日〜2016年8月12日
【調査対象】女川原発周辺自治体(女川原発から30km圏を含む市町)の医療機関・介護福祉施設(以後、「機関・施設等」と称す)114件
【調査方法】対象医療機関・施設にアンケート用紙を送付し、返信封筒で郵送頂いた
【回答率】全体43件(37.7%)
昨年7月に行った調査では女川原発過酷事故に際し、避難計画を既に作成されている施設は1件のみであったが、今回は2件であった。ただし、昨年同様UPZ内は0件であった。
【結果】
設問1.区分(回答率内訳)
病院:20件中11件(55%)
有床診療所:15件中6件(40%)
在宅療養支援診療所(無床診):19件中4件(21.1%)
介護福祉施設等:60件中22件(36.7%)
設問2.所在地(回答率内訳)
女川町:2件中1件(50%)
石巻市:45件中15件(33.3%)
南三陸町:7件中4件(57.1%)
登米市:32件中15件(46.9%)
美里町:10件中3件(30%)
涌谷町:7件中1件(14.3%)
東松島市:11件中4件(36.4%)
設問3.女川原発からの距離
設問4.病床数・施設の規模
病院(回答数11件) 病床総数1183床 平均:107.5床
有床診療所(回答数6件) 病床総数83床 平均:13.8床
介護福祉施設等(回答数22件) 入所者総数1399人 平均:63.6人
設問5.避難計画の作成状況
県では、女川原発の過酷事故に際し、各機関・施設に対し独自に避難計画を作成するよう要請していますが、貴機関・施設で独自の避難計画を作成されましたか?
(43件中) 「はい」: 2件(4.7%)
「いいえ」:41件(95.3%)
「いいえ」の回答(41件中)の作成予定状況
「近日作成予定」:6件(14.6%)
「当分作成の予定はない」:21件(51.2%)
無回答:14件(34.1%)

設問6.未作成の理由(設問5で「いいえ」と答えた機関・施設41件が対象の設問)
作成されてない理由は何ですか?(複数回答可)
作成方法が分らない: 16件(39 .0 %)
情報が不足で作成は困難である:18件(43 .9 %)
現在作成検討中: 6件(14 .6 %)
県・自治体からの説明がないので作成できない:19件(46 . 3 %)
その他: 10件(23 .4 %)
その他に記載された内容
(30km圏外(4件)、施設独自作成は困難、住民との助け合いが必要だから、防衛省施設のため、再稼働させない、法人からの指示がない)
設問7.作成上困難な点
貴機関・施設で独自に避難計画を作成する上で難しい点はどの様な所ですか。(複数回答可 母集団は設問5で「いいえ」と答えた機関・施設41件)
①避難(転医)先の確保: 30件(73.2%)
②情報の収集や誘導体制の確立: 28件(68.3%)
③避難径路の選定: 19件(46.3%)
④避難時の誘導責任者と要員の確保: 17件(41.5%)
⑤車両等避難手段の確保: 29件(70.7%)
⑥関係機関との連携: 19件(46.3%)
⑦避難先での患者・利用者のケア方法: 20件(48.8%)
⑧搬送・移送に必要な資機材の確保: 17件(41.5%)
⑨特に難しいところは無い: 0件(0%)
⑩その他1件、(2.4%)
※その他に記載された内容(衛生部隊単独で避難等行動する事がないため)
設問8.解決責任の所在
設問7における難しい点の解決は何処が責任を持って行うべきだと思われますか?(複数回答可 指摘総数総計数155)
自院・自施設で責任を持って調整・解決する:40件(25.8%)
市町が責任を持って調整・解決する: 48件(31.0%)
県が責任を持って調整・解決する: 67件(43.2%)
*「自院・自施設」・「市町」・「県」の指摘状況を見ると、
・自院・自施設で責任を持って調整・解決する(指摘数40件の割合)
-
避難(転医)先の確保:5件(12.5%)
-
情報の収集や誘導体制の確立:5件(12.5%)
-
避難径路の選定:6件(15.0%)
-
避難時の誘導責任者と要員の確保:6件(15.0%)
-
車両等避難手段の確保:5件(12.5%)
-
関係機関との連携:5件(12.5%)
-
避難先での患者・利用者のケア方法:7件(17.5%)
-
搬送・移送に必要な資機材の確保:1件(5%)
-
特に難しいところはない:0件(0%)
・市町が責任を持って調整・解決する(指摘数48件中の割合)
-
避難(転医)先の確保:6件(12.5%)
-
情報の収集や誘導体制の確立:11件(22.9%)
-
避難径路の選定:5件(10.4%)
-
避難時の誘導責任者と要員の確保:2件(2%)
-
車両等避難手段の確保:8件(16.7%)
-
関係機関との連携:7件(14.6%)
-
避難先での患者・利用者のケア方法:2件(2%)
-
搬送・移送に必要な資機材の確保:7件(14.6%)
-
特に難しいところはない:0件(0%)
・県が責任を持って調整・解決する(指摘数67件中の割合)
-
避難(転医)先の確保:12件(17.9%)
-
情報の収集や誘導体制の確立:9件(13.4%)
-
避難径路の選定:8件(11.9%)
-
避難時の誘導責任者と要員の確保:4件(9%)
-
車両等避難手段の確保:9件(4%)
-
関係機関との連携:6件(0%)
-
避難先での患者・利用者のケア方法:7件(4%)
-
搬送・移送に必要な資機材の確保:12件(9%)
-
特に難しいところはない:0件(0%)
*各項目についての詳細




「責任性」選択の理由(記載15件)
-
避難先確保や避難手段の確保は病院単独で確保するのは難しい
-
県および市のガイドラインに添った対応が必要になるため
-
基本的には自院で賄う予定でおります
-
施設や町での解決は困難
-
原発事故となれば広範囲(遠距離)での避難をよぎなくされる場合がある
-
行政の介入が必要
-
自院で解決するには限界がある
-
全体の把握が困難と思われるため
-
有事の状況により転医先が違ってくるのではないか?避難車輛の確保について、合理的に配車されている事が望ましいと考える
-
問題が大きすぎて民間で対応するのは困難、情報収集が困難
-
個々の企業における判断で避難することではないと思います。広域であれば県、市が対策を考えるべきではないか?
-
女川原発の避難計画等について県や市の立場、権利等が分からない為
-
町自体が全町避難する可能性があり町に避難支援を求めても医療センター老健のみを優先することは不可能。他にも多数の要介護者、要支援者がいる
-
広域的に問題が生じることが予測される為、一事業者での解決範囲ではない
-
女川原発の事故等でどのように移動できるかも分からないし、国さえもきちんと責任、説明をしていないのにどう避難すればいいのかも、手段も分からない



















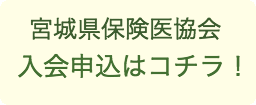
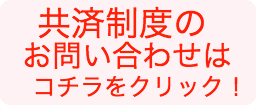
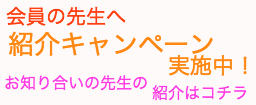
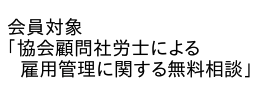



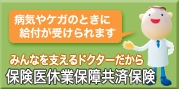
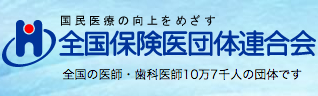

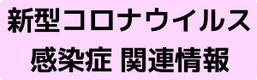
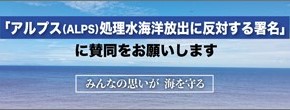
Pingback: 女川原子力発電所過酷事故時における避難計画に関する要望書 | 宮城県保険医協会