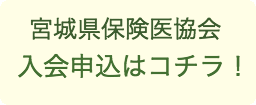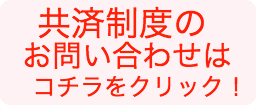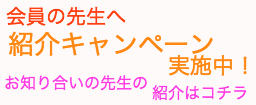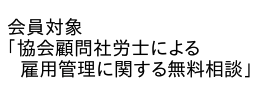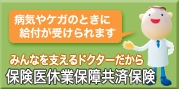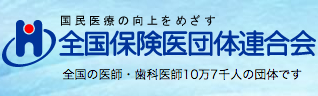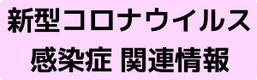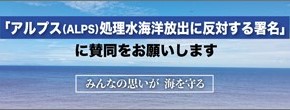シリーズ「女川原発廃炉への道」
あの教訓を再び
エネルギー基本計画から考える
公害環境対策部長 杉目 博厚
第7次エネルギー計画の原案から、東京電力福島第一原発事故以来続いていた「原発の依存性を可能な限り軽減する」との文言が姿を消した。原発回帰路線への大きな転換である。
2024年11月22日、折しもエネルギー基本計画がまとめられる審議の最中に、経団連が経済産業大臣に提言書を提出した。この中で経団連は上記文言を削除し、原発を最大限に活用することや、原発の再稼働、建て替え、新増設、次世代革新炉の開発を求めていた。まさしくこの経団連の提言がそのままエネルギー計画原案に取り込まれたことになる。
岸田前政権が2023年に閣議決定したGX基本方針が出された辺りから、いわゆる「原子力ムラ」が再台頭してきた形だ。原発事故以来、原子力産業はそのサプライチェーンが維持できない危機的状況にあるという。原子力産業維持には原子炉の建て替え、新増設が欠かせないのだ。
つまり、今回の原案は原子力産業を守る為のエネルギー政策といってもよいのではないだろうか。
国民の所得を上げることを訴える国民民主党も原発推進路線だ。同党の玉木代表は石破総理との会談で、原発の建て替えや新増設を提言している。さらにSNS上では、その必要性について「そもそも安価で安定的な電力供給がなければ、賃金も上がらないし手取りも増えません」と主張している。
私には全く理解できない。新型原発の建設コストはその安全性確保のため高騰している。経済産業省はその費用を電気料金に上乗せできる制度を検討中という。安価であろうか? 原発の発電コストが安価ではないことは様々な報告からも明らかであり、米国政府においてはUSEIAが「原発は高い」と認めている。
あの原発事故の教訓から日本のエネルギー政策の基本とされていた「原発の依存性を可能な限り軽減する」という文言は時の流れの中で消え失せてしまってよいものなのであろうか。また再び新たな「原発安全神話」が根拠もなく生まれ、崩壊した「原発は安価な電源」というロジックが現実と乖離した形で生み出され、再生可能エネルギーで十分賄えるエネルギー政策が原子力産業を守るためにその歩みを鈍化させられる。
あの時の教訓はどこに行ってしまうのであろうか。もう一度あの時を思い出し、あの悲劇を繰り返さないという決意を新たにしなければいけない重要な岐路に今私たちは立っている。
本稿は宮城保険医新聞2025年3月5日(1859)号に掲載しました。